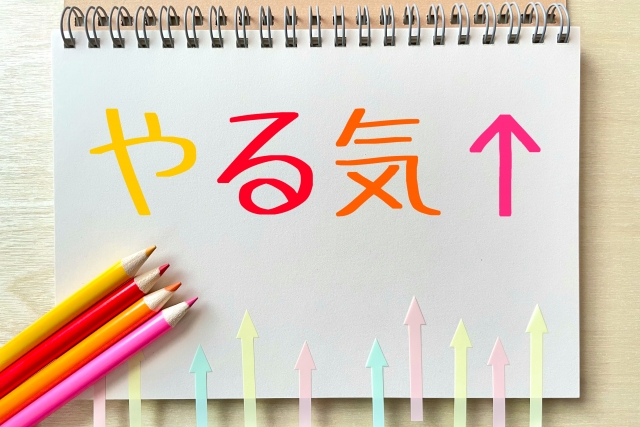賃金はやりがいの「土台」になる

社員のやりがいを高めるために、まず考えるべきは 「賃金はやりがいを直接生むものではないが、不足すると大きな不満につながる」という点です。
心理学者フレデリック・ハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」によれば、賃金は「衛生要因」に分類されます。これは、「満たされないと不満を生むが、満たされたからといって強いモチベーションにつながるわけではない」という性質を持っています。
例えば、給与が低すぎると、社員は生活の不安や不満を抱え、仕事への集中力も低下します。
しかし、上記の理論によると、給与が適正である場合でも、それ自体が長期的なやりがいの源泉になるわけではありません。つまり、賃金は「やりがいを感じるための最低条件」であり、給与だけでやりがいを生み出すのは難しいのです。
賃金がやりがいにプラスの影響を与えるケース

しかしながら、適切な賃金は、社員のやりがいを支える重要な要素になります。それは以下のようなケースです。
評価の納得感がある場合
社員は、自分の成果や努力が適切に評価され、それが給与に反映されていると感じたときに、やりがいを強く感じます。
- 例:成果主義の企業で、売上成績が給与に直結している場合
- 例:昇給のプロセスが明確で、公平な評価制度が整っている場合

評価の透明性が高いほど、社員は「自分の努力が正しく報われている」と感じ、仕事へのモチベーションが向上します。
生活の安定が確保されている場合
給与が生活水準を満たしていないと、社員は仕事のやりがいよりも「生活のために働く」ことが優先されてしまいます。
- 例:基本給が市場相場より低く、社員が副業や転職を考えざるを得ない状況
- 例:生活コストの上昇に対して給与が追いついておらず、不安を感じる場合
十分な給与が確保されていると、社員は仕事の内容や成長に集中でき、やりがいを感じやすくなります。
業界や職種による影響
業界や職種によっては、賃金が直接的なモチベーションに影響を与える場合もあります。
- 営業職・歩合制の仕事:インセンティブが明確で、給与が成果と直結するため、やる気が高まりやすい。
賃金がやりがいにマイナスの影響を与えるケース
一方で、単純に賃金が高ければ高いほどやりがいが増すわけではありません。むしろ、以下のような場合には、賃金がやりがいを損なう原因になることもあります。
賃金に対する不公平感がある場合
給与が市場水準より低かったり、同僚と比べて明らかに低いと、社員は「評価されていない」と感じ、やりがいを失います。
- 例:「同じ仕事をしているのに、自分だけ昇給しない」
- 例:「他社の同じ職種と比べて給与が低いと感じる」
優秀な社員ほど、市場価値を意識するため、給与の適正性を確認する傾向があります。不公平感が強いと、離職につながるリスクも高まります。
また、給与の高さだけでモチベーションを維持するのではなく、仕事の意義や成長の機会を同時に提供することが重要 になります。
まとめ
- 賃金は、やりがいの土台となるが、それだけでは長期的なモチベーションにはつながらない。
- 適正な賃金と、公平感のある評価制度が、やりがいを支える鍵となる。
人材マネジメント施策のご相談をお受けします
会社が成長していくうえで人材マネジメントは重要なポイントになります。
ヒューマンキャピタルは豊富な経験と専門性を元に、丁寧なヒアリングと綿密なミーティングをもってクライアント様に最適な人材マネジメント施策をアドバイスをさせていただきます。
ぜひ一度、ご相談ください。

投稿フォームからご相談、お問い合わせください
*********************************
投稿フォームはこちらです
*********************************